広告・編集方針について
開示条件:記事作成にあたりメーカーから金銭的な対価は一切受けていません。コンテンツ内容にメーカーや広告主による影響はありません。記事内に広告が含まれています。
「おうち防災」とは、 停電・断水・通信断が同時に起きても 60日間 《電力・水・情報》を自給自足できる 家庭用レジリエンス設計 である。
私たちは、地震・台風・豪雨・噴火といった多様な災害が複合的に襲いかかる列島に暮らしています。
災害の発生時刻や規模を正確に予測することは、現時点の科学技術では困難です。しかし、「被害をどれだけ小さくできるか」という点については、私たち一人ひとりが具体的な対策を講じることができます。
「いつか来る大災害」に備えて、何から始めればいいのでしょうか?
高額な設備投資が必要?専門知識がないと無理?家族の協力は得られる?
この記事では、専門的な知識がなくても段階的に実装できる「家庭版・減災ポートフォリオ」を、具体的なポータブル電源選定から運用方法、費用対効果まで紹介します。
目標は「60日間の自立生存」。必要な投資額は25万円から始められる現実的なプランです。
この記事でおすすめしているポータブル電源・ソーラーパネルセットは「BLUETTI Elite 200 V2 + 350Wソーラーパネル」です。
実機レビュー ▶︎ 【最高水準の品質と信頼性】BLUETTI Elite 200 V2
私も勉強しながら記述しています。ご意見やアドバイスがございましたら、コメント欄からお寄せください!
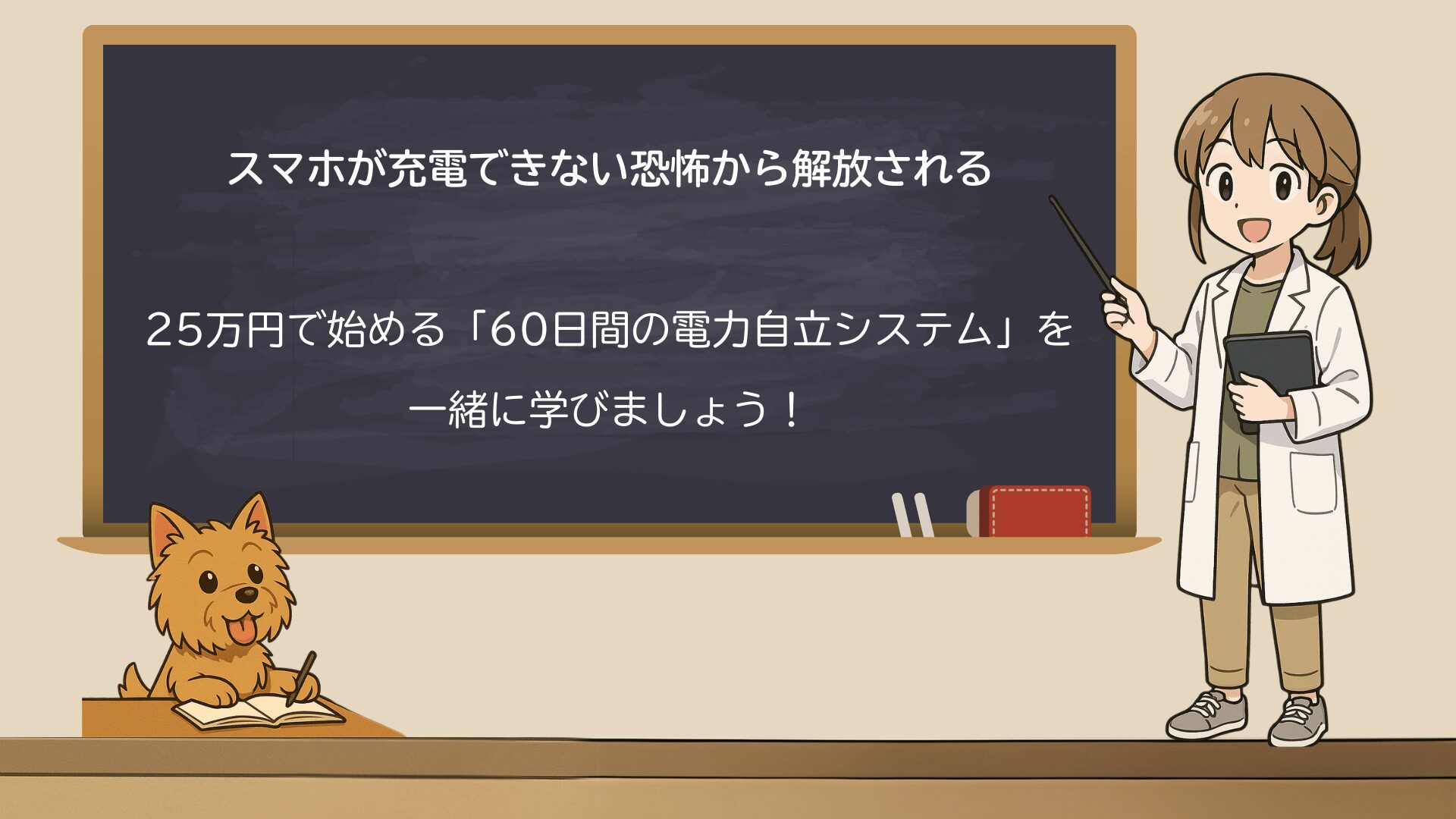
音声で聞く:ゲーム感覚でレベルアップ!災害対策「減災ポートフォリオ」のススメ
「この記事、ちょっと長いな…」という方へ。
記事のポイントを音声でまとめました!「災害対策=ゲームのレベル上げ」としてわかりやすく解説します。
▶︎ YouTubeで聴く
はじめに:”おうち防災”という考え方
高校生にもわかる!——「レベル上げ+弱点カバー」の理屈
リスク=ダメージ確率 × ダメージ量
- 停電は起こる確率が高いけどダメージ量は中。
- 大地震は確率は低くてもダメージ量が大。
- → 両方カバーする装備をそろえると効率がいい。
大規模災害は 確率論 × カオス です。
「発生時刻や規模を完璧に当てる」ことは原理的に不可能でも、 損失期待値 E[L] を最小化する戦略 は論理的に設計できます。
E[L(D,p,s,t,c)]=w1(人的被害)+w2(機能喪失日数)+w3(経済コスト)+w4(心理的損耗)
災害スペクトラム:地震 / 津波 / 台風・豪雨 / 洪水・高潮 / 土砂災害 / 落雷 / 火山灰 / 寒波・猛暑 / パンデミック / 停電・通信断 / 燃料・物流遮断 / テロ・CBRN(化学・生物・放射性・核)
制御不能パラメータ:発生確率 p , 強度 s , 継続時間 t , 同時多発性 c 。
目的関数に対し、個人レベルで取り得る”理論上の最適解”を分解しつつ、予算や住環境に合わせて段階導入できる実践フレームに落とし込みます。
ざっくり言うと── “自宅をライフラインごと要塞化して、60日間は誰の助けも借りずに生き延びられる仕組みをフルセットで作っちゃえ!” というのが理論上の”完璧プラン”です。
電力レジリエンス:自宅を”ミニ発電所”にする
「ゲームのライフを減らさない」作戦
① 電気をためる
ポータブル電源を家に1つは置く → 暗くてもスマホやライトが使える 充電=ゲームのセーブデータ。停電しても”セーブ”が消えないようにする
1-1 バッテリーシステムとポータブル電源のハイブリッド
最初に押さえたいのは「単一機器で完結させない」こと。リン酸鉄リチウムイオン電池ベースの据置型バッテリーシステム(20 kWh級)は、 太陽光発電と組み合わせることで、冷蔵庫とエアコンを60日間運用可能なエネルギー環境を構築できます 。
日中はソーラーパネルから充電、夜間にバッテリーから供給する”昼充電・夜放電”の運用が前提です。ところが地震で基礎が歪むとシステムごと停止するリスクがある。
そこで、ポータブル電源(2,000Wh×2台)を常にフル充電で待機させておきます。
ホームバックアップがダウンしても、ポータブル電源で最低限の出力を確保できる構成です。
試算:冷蔵庫+エアコンを60日動かすと?
▼冷蔵庫(例:省エネ型400Lクラス) 消費電力:1日あたり約1.0〜1.2kWh 60日分:約60〜72kWh
▼エアコン(6畳用・冷房時/中運転) 消費電力: 1日あたり1.2〜2.0kWh程度(地域差あり) 60日分: 約72〜120kWh
合計消費電力量(目安)
| 電気機器 | 60日合計(低〜高) |
| 冷蔵庫 | 60〜72kWh |
| エアコン | 72〜120kWh |
| 合計 | 132〜192kWh |
1-2 多重発電ソース
- 固定PV3kW :晴天時は日中ロード+BESS充電をほぼ賄える。
- 折りたたみPV400W×2 :陸屋根やバルコニーしかない都市部のマンションでも展開可能。
1-3 UPS機能と瞬低対策
BESSをUPSモードで運用すると、系統停電から15秒以内に自動切替。BLE通信のスマートメーター連動で商用復帰も自動化し、ブラックアウト時のトラブルシュートをゼロにします。
水と衛生:”質”より”連続稼働性”
② 水とごはんをストック
水2リットル×家族人数×7日分
のどがかわく・おなかがすく=ゲームオーバー直行 「ライフ回復ポーション」を毎日持っているイメージ
井戸を掘れないタワマン居住者でも、自治体が公開する災害時給水栓や公園井戸の座標をGIS化し、徒歩15分圏を網羅しておくと”拡張タンク”になります。手押し兼DC12V駆動のROポンプを合わせて携帯すれば、濁水でも1hあたり20L以上処理できます。
私は、自宅とは別に井戸水が出る敷地を購入しました。200km以上離れているので、どちらかは災害時に使えると想定しています。
とはいっても、なかなか難しいのでペットボトルのお水を用意しておきましょう。
備蓄用の飲料水や食料は以下の記事で紹介しています。
通信レジリエンス:「つながる」は命綱
③ 情報を2つ以上でチェック
スマホ+ラジオ → デマにだまされにくい “ミニマップ”と”仲間のチャット”を両方見る感じ
1層目は光回線+無停電電源。2層目としてStarlink Roamを導入すると、衛星-地上遅延は100ms程度でテレワークにも耐えます。99.5%のリンク可用性は、実測的には年間平均43hのダウンにしか相当しません。
最後のバックアップはIridium衛星電話とHF無線(NVIS運用)。音声とテキストしか送れませんが、行政情報と家族連絡は最低限維持できます。
通信冗長は「行政情報を受け取る」「助けが必要な人を炙り出す」「物資共有をオンラインで調整する」の三役を一気に担い、 人的被害 w₁ の重みを大幅に圧縮 します。
食料とバイタルケア:60 日を設計パラメータに
レベル上げ=基本3資源を強化
| 資源 | 目安 | なぜ? |
| 電気 | 1kWh/日を7日分 → 1.5kWh級ポータブル電源を2台 | 生活家電+携帯充電のエネルギー需要をカバー |
| 水 | 4 L/人/日を14日 | 体の60%が水分。脱水2%で集中力低下 |
| 情報 | LTE⇄衛星⇄FMラジオの二重化 | 通信の”シングルポイント・オブ・フェイル”を潰す |
- フリーズドライ30日分(4,000kcal/日) :フリーズドライ(主食+タンパク)」は 30日で消費し、常に賞味期限 5年残しで入れ替える”ローリングストック”。
- MRE30日分 :加熱反応パックで調理火力を節約。
- NFT 水耕栽培で「食感と彩り」のメンタル維持 :葉物 1 m² は 1クール 10日で700g。家族4人で一日80gのサラダが確保でき、 ビタミン K・葉酸・食物繊維が不足しません。LED消費は60W なので、昼間のPV余剰で十分まかなえます。
モビリティと退避フロー:”動ける要塞”の思想
④ 家の安全チェック
家具の固定・懐中電灯の場所確認 → HP(けが)を減らさない ボス戦前に装備を整える
| レイヤー | 移動手段 | 主な役割 |
| 一次 | AWD EV(75kWh, V2L 6kW) | 自宅用BESS が故障しても 10kW h/日×6日の代替 |
| 二次 | 折りたたみ電動バイク(航続 40km)+インフレータブルカヤック | 道路閉塞・浸水域を突破 |
| 三次 | 徒歩退避パック(15kg・ポータブル電源 200Wh+40Wソーラーパネル入り) | 最悪徒歩でも 48h 生存 |
道路が塞がれるリスク=p₁、浸水=p₂、燃料入手不可=p₃ とすると、EV+人力ハイブリッドで p₁×p₂×p₃ の積を分離 でき、退避失敗確率が指数的に減少する点がポイントです。
優先順位とコスト曲線:どこから手を付けるか
弱点カバー=環境ごとの”ボトルネック”を先読み
- マンション高層:停電復旧は速いが断水しやすい→ 給水ポンプが止まる
- 戸建て郊外:電柱倒木・長時間停電→ 屋根ソーラーで自給
- 車中泊:燃料不足→ 走行充電器と折りたたみソーラーで回避
| フェーズ | 主な投資 | 期待効果 | 概算費用 |
| Phase 0 | ポータブル電源 2kWh+折りたたみPV400W | 停電被害回避 | 25万 |
| Phase 1 | 据置BESS 8kWh+固定PV1.5kW | 3日島モード | 120万 |
| Phase 2 | 据置BESS 20kWh+PV3kW+Starlink | 30日島モード+遠隔勤務維持 | 250万 |
| Phase 3 | EV+風力+医療CBRN+水耕栽培 | 60日完全自活 | 500万 |
- 停電対策は費用対効果が最も高い
- 200Wh/日×家族 = ライフライン体感の7割を占める。
- 水は”質”より”連続稼働性”
- 電動ポンプ専用 UPS(LiFePO₄ 1kWh)が 1台あるだけで安心度が段違い。
- 通信は Starlink がゲームチェンジャー
- 月額 ~1万円で99.5%可用性 。行政情報もテレワークも維持。
- 食料と医療は漸次拡張
- まず14日、次に30日、最終目標60日。
ROIの分解思考:停電3日で冷蔵食品ロス2万円、ホテル避難4人×2泊で 10万円、テレワーク損失(フリーランス) 8万円とすると、1回の災害で20万円前後が飛ぶ計算。Phase 1 への投資は1回の災害で原価償却できる水準です。
オペレーション:技術を”筋肉化”する
- 月1回 24hの完全無人島モード :実際にブレーカーを落とし、冷蔵庫・調理・入浴をポータブル電源だけで回すと「電力の引き算感覚」が身につきます。
- 半年1回 48h無補給訓練 :飲料水の補給や保存食の調理法を家族と共有。一連の動きが自動化されると、心理的負荷が大幅に低減
- Home-Assistant統合ダッシュボード :震度計・水位計・放射線量・BESS SoCをリアルタイム表示し、閾値を超えたらLINEで自動通知。
- 退避シナリオA/B :在宅継続/車両避難を5秒で判断できるIF-THENツリーを家族で共有。
“完全”の定義を再構築
余力(冗長性)が2重化したら「完璧」に近づく
- 例えばポータブル電源2台+ソーラーパネル:1台故障でももう1台が残る。
- 水:ペットボトル備蓄+家庭用浄水器。
結論:ダメージ式の”最大値”を下げること=完璧に近づくこと。
- ブラックスワン (極端事象)は排除しきれない。
- よって 残余リスク を”主観的に許容できる閾値”未満まで下げた状態を「完璧」と再定義。
- これを満たす最小投資額(マンションケース)≈ 100万円。以降の投資は限界効用が急減。
まとめ:ポイントは「同じ手段を重ねず、性質の違うバックアップを重ねる」こと
収束点 :冗長性(backup)、多様性(別系統)、可搬性(持ち出し)が3本そろうと、個人の リスク×コスト積は理論的に最小化される。これが「完璧に限りなく近い備え」のロジックです。
実際には住環境・法規・予算という制約が必ず存在します。
まずはPhase 0でポータブル電源とソーラーパネルを手に入れ、「停電中の冷蔵庫とスマホ充電」を確実化し、停電 1日目のストレスを削るだけでも、被害期待値 E[L] は着実に下がります。
具体的には、「BLUETTI Elite 200 V2 + 350Wソーラーパネル」をおすすめします。
- 電源の二重化 だけでも災害時ストレスは劇的に下がります。
- 水と通信 をもう 1 段追加すれば、家族の安全曲線は指数関数的に上昇します。
成功体験が積み重なるほど、次のフェーズに進むモチベーションが高まり、結果として家族やコミュニティ全体のレジリエンスが底上げされます。
ポータブル電源 × レジリエンス は、単なるガジェット趣味を超えて「生活を守る工学」そのもの。
当ブログでは、今後も 停電・災害対策情報や最新ポータブル電源の実機レビュー を通じて、みなさまの”減災ポートフォリオ”構築を支援していきます。

